一般人がお坊さんになるにはどうしたら良いの?お坊さんってすごい修行しないと成れないんでしょ?などと最近尋ねられることが多くなったので、本記事では現役僧侶がお坊さんになる方法を解説します!
とはいえ、お坊さんになると言っても日本には多くの宗派があり、それぞれの宗派によってお坊さんになる方法は違ってくるのが実情です。それこそ厳しい修行をしないとお坊さんになることができないという宗派もあります。
私は、京都の東本願寺を本山とする真宗大谷派という宗派に属しているので、この記事では真宗大谷派のお坊さんになる方法を解説しますが、他の宗派でも似ていたりするところもあるので参考になるかもしれません。
- お坊さんになるための手順が知りたい
- お坊さんに資格があるのか知りたい
- お坊さんになるための費用が知りたい
まずお坊さんになるための具体的な流れとしては以下の通りです。
これから1ステップずつ解説していきますが、本記事がお坊さんになりたいという志をお持ちになった方の一助となることを願っています。
所属寺(手次寺)を見つける
まず、一般人がお坊さんになるための第一歩として、所属寺(手次寺)を見つける必要があります。
なぜなら真宗大谷派では、僧侶は必ずどこかのお寺に所属しないといけないと決められているからです。
これがお寺生まれの場合、生まれたお寺が自動的に所属寺になるので、難しく考える必要はありませんが、一般人の場合だと、何らかの方法で所属するお寺を見つける必要が出てくるのです。
さらに所属寺は、スマホの契約会社を変えるように、ぽんぽんと簡単に変えることはできません。お寺同士は横のつながりもあるので、このお寺に所属しようと思ったけどやっぱりやーめたと簡単に変えることはできないのです。
自分に合った所属寺を最初から見つける必要があるので、慎重に行わなければなりません。
僧侶となるためには所属する住職の同意も必要となります。
良いお寺を見つけたら「お坊さんになりたい」という意思をしっかり伝え、協力いただけそうなお寺に所属するということが肝心です。
万が一、住職があなたが僧侶になることに協力的ではない場合、いくらあなたが研鑽を積んだところで、お坊さんになれないということにもなりかねません。
それこそ、住職も一人の人間ですから、すごく親身になってくれる住職もいれば、残念ながらそんなことは認めんと頑固な住職もいるのが現実です。
はっきり言って、何も伝手がない一般人がお坊さんになろうとした場合、この所属寺を見つけることが一番のネックになると思います。
研鑽を積む
めでたく所属寺を見つけることができたら、次はお坊さんになるためにお経を読むことができるかという声明(しょうみょう)作法であったりを身に着ける必要があります。
なぜなら、お坊さんになるためには、後で説明する「得度考査」というものを受ける必要があるからです。
もちろん作法も大事ですが、なぜお坊さんになりたいのか?ということをはっきりさせておくことも大切です。併せて仏教の基本的知識も身に着けておく必要があります。
これらを学ぶ方法はいろいろありますが、所属寺するお寺の住職に学ぶということが一つの方法です。また今はYouTubeなどで、お経を読んでいる動画等も上がっているので、独学で学ぶこともできなくはないです。
また、教務所や別院によっては、声明教室をやっているところもあったりするので、そういった研修を利用するのも手でしょう。
住職の同意を得る
十分僧侶になるための研鑽が積み終わったら、次はお寺の住職にお坊さんになることの同意を得る必要があります。
住職としても、見ず知らずの人を自分の寺の僧侶にしたいと思うはずがありません。住職は自分のお寺に所属する僧侶を監督する責任があります。もし、僧侶になったあなたが問題を起こした場合、住職としての面目が丸つぶれになってしまうことにもなるのです。
そのため、住職の同意というものは単純に許可を得れば良いというわけではなく、ぜひこの人に僧侶になって欲しいと住職に思ってもらう必要があるわけです。
こう書くと住職の同意を取るというのは難しく感じるかもしれませんが、結局は人間関係です。住職との関係が良好であれば、特に問題になることはないかと思います。
所属寺を決める時点で、お坊さんになりたいということを伝え、住職の元で研鑽を積んできたならば、住職との信頼関係も出来あがっていることでしょう。
得度願を提出する
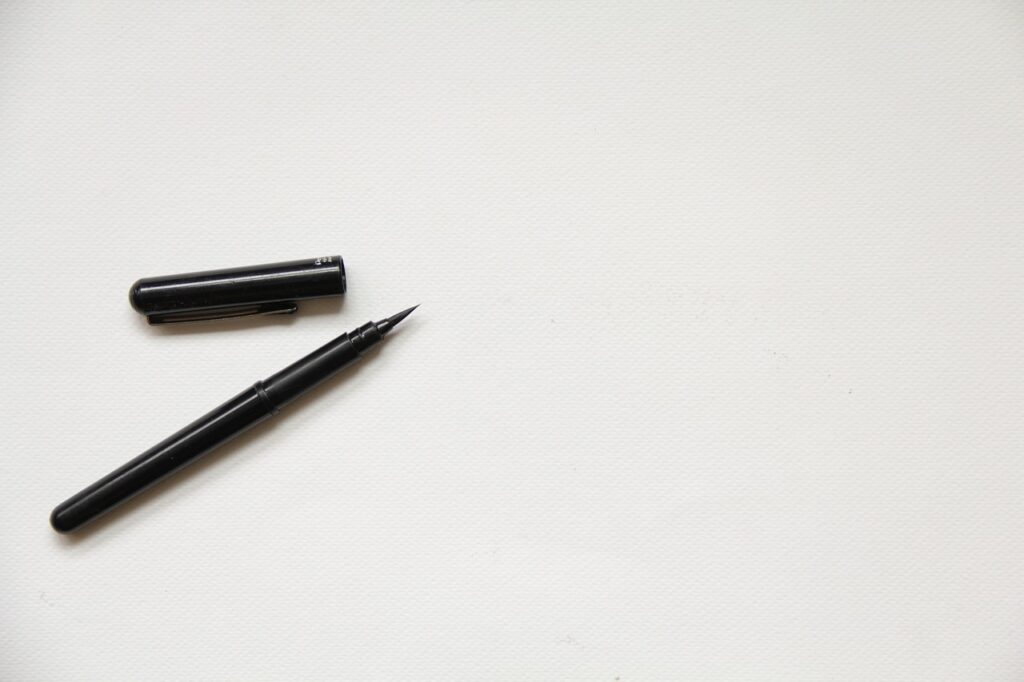
住職の同意を得ることができたら、所属寺所轄の教務所に「得度願」を出したいことを伝え、書類をもらいましょう。
書類には自分の署名と所属寺住職の署名と組長(そちょう)の署名が必要になります。
組長の署名押印は住職に署名することと併せて、住職にお願いすれば署名押印していただけます。
その他にも住民票や身分証明書が必要となりますので、慌てないように準備しておきましょう。
得度考査を受ける
得度願を教務所に提出したら、次に得度考査を受ける必要があります。
そのため、読経作法をここまでにしっかり学んでおきましょう。
得度考査は、特別な理由がない限りは、所属するお寺を管轄している教務所で受けることになります。
得度考査の内容
得度考査は、資格試験のように日時が決まっているわけではなく、随時行われています。
試験内容は年齢によって変わってきますが、主に「読経が正しくできているかどうか」「作法が正しいかどうか」「僧侶としての心構え」などがチェックされます。
- ~13歳まで 阿弥陀経、正信偈(草四句目下)、念仏和讃三匋
- 14歳~16歳 無量寿経上巻、正信偈(草四句目下)、念仏和讃三匋
- 17歳以上 浄土三部経、正信偈(草四句目下)、念仏和讃三匋
得度式を受式する
得度式は、本山である京都・東本願寺で執り行われます。
受式日は、年に何回かありますが、毎年変わってくるので教務所にいつ行われるのか確認しておきましょう。
得度式当日の具体的な内容は下記記事で解説していますので、参考にしてみてください。
得度式を受式を終えたら、晴れて僧侶となりますが、僧侶=住職になれるということではないので注意が必要です。
住職になるためには、さらに研鑽を積み「真宗大谷派教師資格」という資格を取得する必要があるからです。
そのためにも、引き続き研鑽を積んでいきましょう。
お坊さんになるためにかかる費用
最後にお坊さんになるための費用ですが、得度を受けるための礼金として10万円が必要です。
その他に衣体(僧侶の衣)の購入費用や経典類の購入費用がかかってきます。購入する店舗によっても変わってきますので、一概に言えませんが、10万円~20万円程度みておくと良いでしょう。
その他には、京都までの往復分の旅費なども必要です。
どんなに多くても50万円を越えることはなく、大体平均して30万円程度ではないでしょうか。
参考にしてみてください。


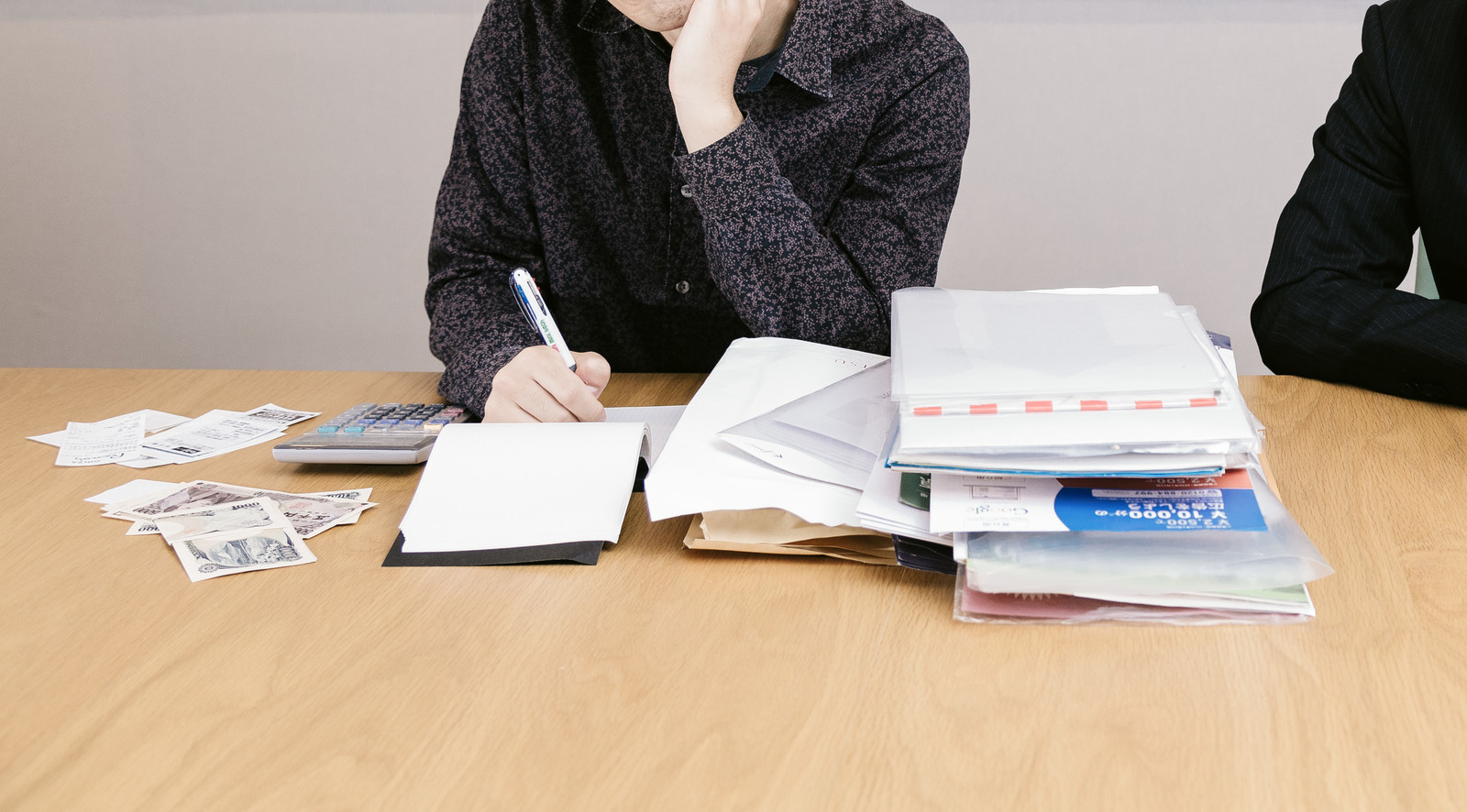
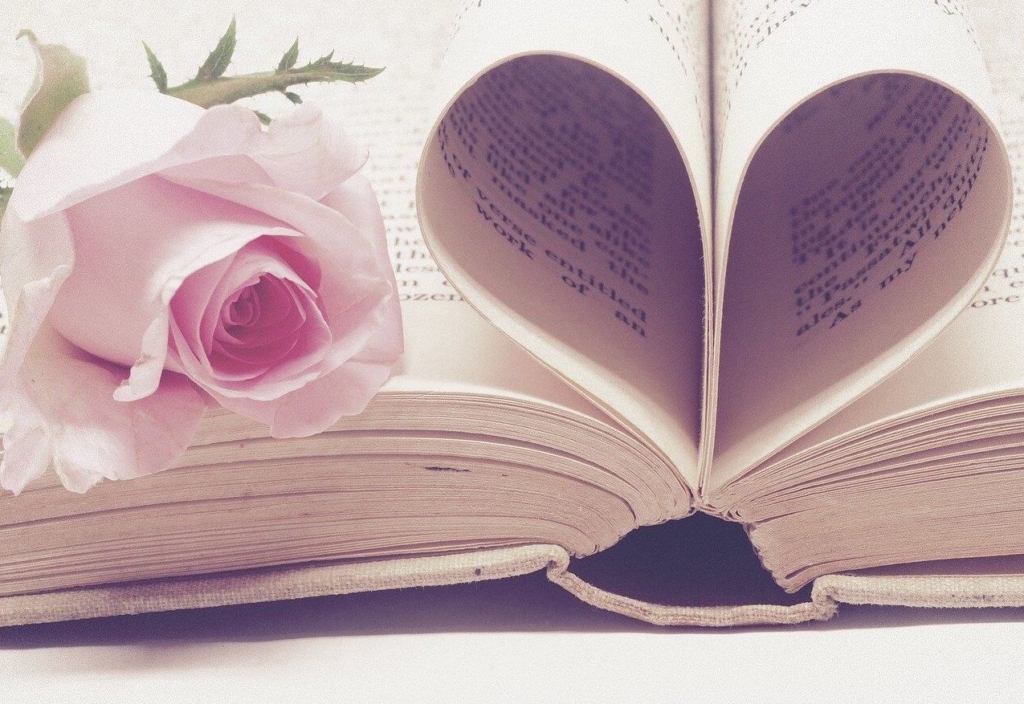





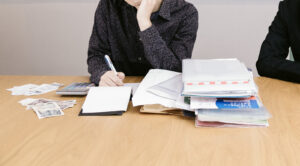


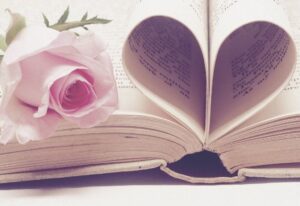


コメント