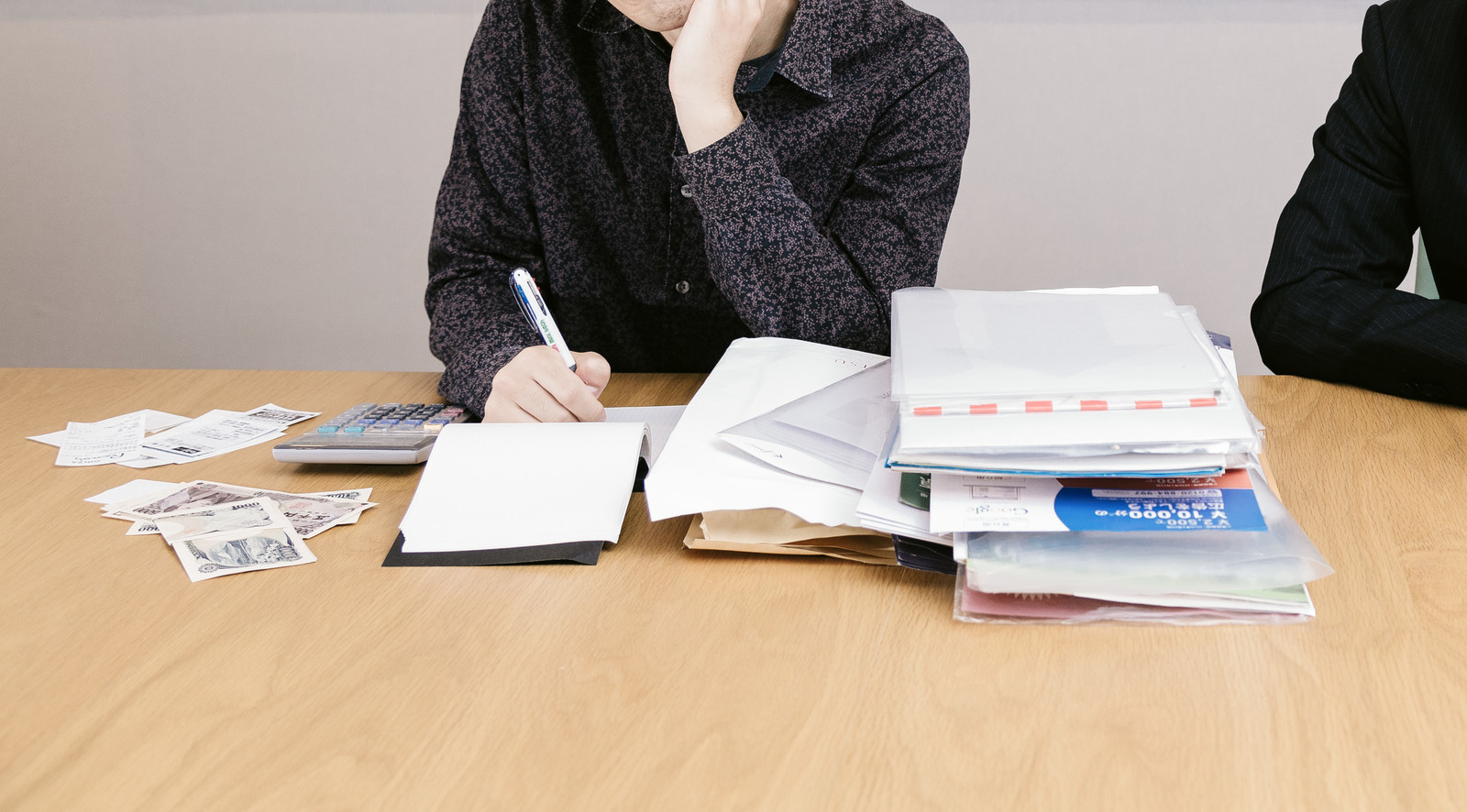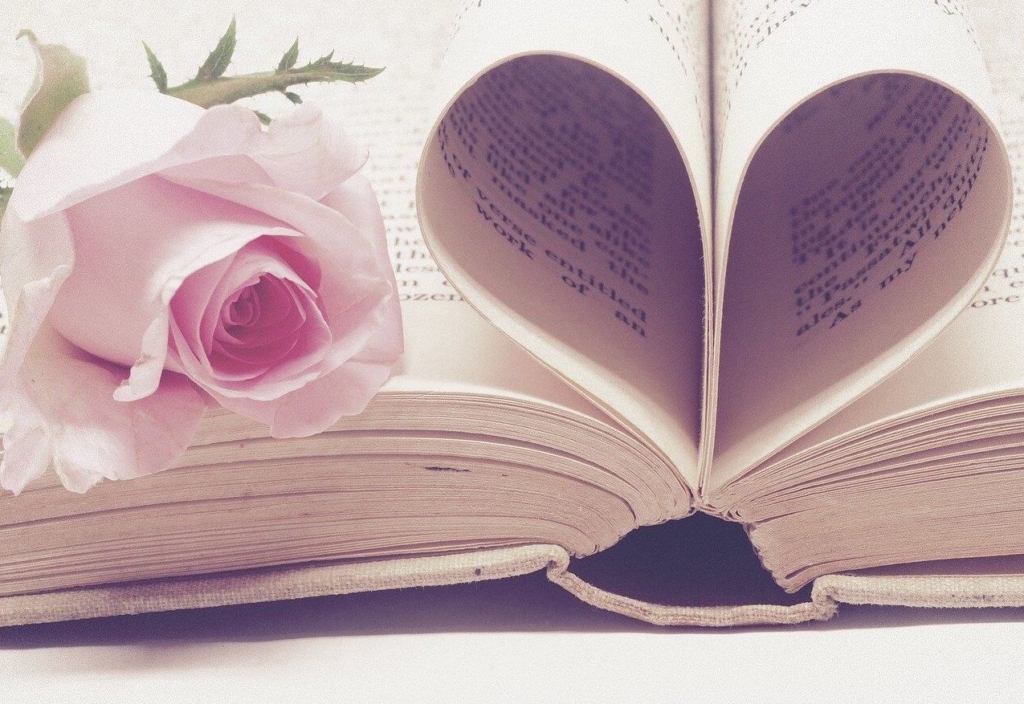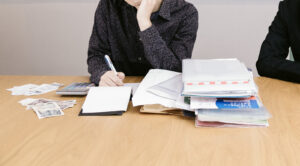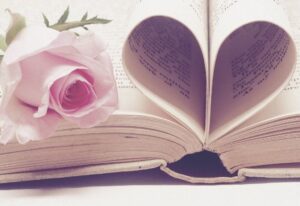僧侶の仕事のイメージとして法事や葬儀に行っているというのは誰でも想像することができると思います。
ではそのお坊さんのお嫁さんは普段何をしているのでしょうか?
専業主婦?それとも全く関係ない仕事をしているのでしょうか?
私自身僧侶ですし、知り合いの僧侶の友人もたくさんいますので、実際に聞き取りを行ってみました。
本記事では、実際に友人の僧侶やそのお嫁さんに聞き取りを行って分かった「僧侶のお嫁さんがしている仕事」をご紹介します。
- お坊さんの奥さんの具体的な仕事内容が知りたい
- 今度お寺に嫁ぐので、必要になるスキルが知りたい
- お坊さんの奥さんって実際大変なの?
お坊さんの奥さんの具体的な仕事内容
まず大前提として、お寺は夫婦やその家族で運営されていることがほとんどです。
自営業の経営をイメージしてもらえるとわかりやすいと思います。
お坊さんの奥さんは住職がお参りに出ている間、場合によっては一人でお寺を任されることになるので結構責任重大です。
お寺のお嫁さんがやる仕事と言えば、お坊さんを支える裏方的な役割が多いんじゃないの?と思われる人も多いかもしれませんが、結構表舞台に立つことも多く、お寺は夫婦二人で運営していくものというのが実際のところです。
それでは、実際に仕事内容を詳しく解説していきます。
鐘付き

お寺から響くゴーンゴーンという鐘の音。
大晦日には馴染みのあるお寺の鐘の音ですが、日常的に鐘は付いています。
お寺の鐘には法要が始まる時刻を知らせるという意味があります。
地域差がありますが、要が始まる30分〜1時間前に鐘を付いているというお寺が多いです。
そして、多くのお寺では朝に勤行を毎日勤めているので、朝早くに鐘がなることが多いです。
都会ではなかなか見られない光景ですが、田舎で周辺に住んでいる人は、「鐘がなったな、そろそろ寺に向かうか」と家を出る合図にするんですね。
鐘付きは、住職や信者さんがやる場合もあるのですが、住職は法要の準備などで大忙しという状況。
そのため、鐘はお寺のお嫁さんが付くことになっている場合も多いです。
御仏供のお供え
お寺では、毎日朝ごはんを食べる前に必ず「御仏供(おぶく)」と呼ばれるご飯を仏様にお供えします。
大体1合分くらいを毎日お供えしていることが多いです。
なので、朝食はパン派であったとしても、お寺では必ず毎日ご飯を炊くことになります。
毎日ご飯を炊くとなると、パンを食べることがなくなっちゃいそうですね。
また「御仏供」は、専用の道具を使って作ることになりますが、最初は結構難しいです。
私も僧侶なので、日々御仏供を作ったことはもちろんありますが、絶妙な力加減が必要で慣れるまで時間がかかりました。
ただ2〜3回作れば、コツを掴めると思うので心配はいりません。
お供えした「御仏供」は、お昼ご飯を食べる前にお下げし、お昼にいただいたり冷凍します。
当たり前ですが、ご飯はカチカチになってしまっているので、チャーハンにするなど一工夫が必要です。
掃除

掃除は一般家庭でもやると思いますが、お寺は規模が違います。
普段住んでいる家はもちろんのこと、広い部屋を持つ本堂や、境内も掃除しておかなければなりません。
お寺には、普段から人がたくさん来るのでサボることもできませんしね。
なので常に綺麗にしておいて、いつ誰が来ても良いようにしておかないといけないのが大変です。
広大な面積を掃除しないといけないため、いかに効率よく掃除をするかが問われてきます。
さらに、お寺には仏具であったり、お供え物をもらったりと結構物が溜まりがちな傾向にあります。
それらをいかに効率よく整理するかが、腕に見せ所でもあると思います。
ただし全部お嫁さん一人でしなければならないということはなく、檀家の人たちと一緒になって掃除するイベントを行っていたりもします。
来客対応
お寺は人が突然訪ねてくるというということことが結構あります。
大きいお寺の場合は、住職がお参りにずっと出ていることが多いので、その間の来客対応はお坊さんの奥さんが行うことになることが多いです。
お参りに来る人はもちろんのこと、野菜を届けに来ただけであったり、世間話をしにくるおばあちゃんもいたりしますし、お寺は宗教施設なので信仰相談に来られる方もいらっしゃいます。
住職がいれば、住職が対応することもできますが、前述の通り外に出ていれば信仰相談もお嫁さんが聞くということもあり得ます。
お嫁さんがお参りに行くことはほとんどないと思いますが、少なからず仏教のことを勉強しておく必要はありそうですね。
電話対応

来客だけではなく、お寺には電話がしょっちゅうかかってきます。
「今度誰々の三回忌をやりたいんだけど、ご都合はどうでしょう」
「法事で準備することを教えてください」
などの法事の問合せはもちろんのこと、
「つい先ほど、主人が亡くなりまして・・・」
と深夜に枕経をお願いされることもあります。
住職が不在の場合は、当然奥さんが対応することになります。
電話対応は、聞くべきことを聞けば済みますが、田舎の方だと、方言で聞き取れなかったりするので、そっちのスキルの方が大事だったりもします。
行事の企画や準備
お寺には、お盆やお彼岸以外にも様々な行事があります。
村合同で先祖の供養のための法要を行ったり、研修会など結構頻繁に開催されているみたいです。
行事が頻繁に開催されるということは、その都度事前の案内や会場の準備などをする必要があります。
もちろん、奥さん一人ですべての準備をやるわけではないですが、住職と一緒に行事の企画や準備などを進めていくことになるみたいです。
奥さん主体で研修会やお茶会を組んだりすることもあったりするみたいで、企画力が問われますね。
法衣の洗濯

法衣のお洗濯も、住職の奥さんがやることが多いです。
黒い衣の下に着る白色の白衣という着物があるのですが、これ分厚く、結構汗をかいてしまいます。
だから清潔に保つには、大きな衣を毎日洗って干す必要があるので結構重労働です。
また、お坊さんは靴下ではなく足袋を履いています。足袋は白色なので1日であっという間に汚れてしまいます。
さらに足袋は、なかなか汚れが落ちず、毎日たわしでゴシゴシと洗わないといけないです。
消耗品の発注や買い出し
お寺は、一般社会で言えば事業所なので事務用品や一般家庭では使わないような消耗品も揃えておく必要があります。
さらに、お寺の法要には蝋燭や線香、炭などが必要になりますし、仏具を整備するための道具であったりといろいろな道具を揃える必要があります。
大きなお寺では、それらをまとめて仏具店に発注するという仕事が発生しますし、小さなお寺では奥さんが通常の買い物のついでに買ってくるということもあります。
特に頭を使うのがお寺の経費として落とすものについては、領収書をもらってこなければいけません。
お花立て
お寺の本堂には立派なお花が飾ってありますが、あのお花も奥さんが活けるというお寺が多いです。
お寺のお花にはちゃんとした流派があり、独特のお花の活け方を覚えるのが最初は大変とおっしゃっていました。
しかし、慣れてくると季節の花だったりをポイントに使ったりと結構楽しくなってくるそうです。
私の友人のお寺は、活花に使うお花を買ってくるのではなく、境内で育てているお花を使っています。境内でお花を育てるのも楽しそうですね。
大きいお寺だとお花も大きくなるので、専門の業者に依頼したり、活花で活躍されてる他のお寺の僧侶に来てもらうこともあるのだとか。
経理・事務

お寺は宗教法人なので、毎日の収支計算を行わないといけません。
お布施を誰々さんからいくらいただいたか、住職へ給料をいくら支払ったか、消耗品でいくら使ったのかはすべて帳簿に付けて管理しています。
もちろん年度末には決算資料の作成なども行います。
事務作業としては、他にもお寺に所属している門徒の氏名や法名の管理などもパソコンを使って整理しているみたいです。
お寺といっても結構事務仕事はたくさんあるみたいですね。
大きなお寺だと専門の会計士に頼んでいたり、経理の人を雇用していたりすることもあるそうです。
これは自営業でも一緒かもしれませんね。
まとめ
こうして仕事を一覧で見てみると住職の奥さんの役割がいかに重要かわかります。
実際に話を聞いてみると、ただ単にお坊さんの奥さんというだけではなく、お寺の共同経営者と言った方が良いかもしれませんね。
お寺の奥さんやらないければいけない仕事は多く大変ですが、同時にやりがいも感じている奥さんも多かったです。
言い換えれば夫婦の信頼関係があってこそとも言えますね。